今回は前回の続き(膝離断性骨軟骨炎ってなに??① 〜どんな怪我??〜)で
膝離断性骨軟骨炎の症状や診断の基準について解説したいと思います!
1.どんな症状??
膝離断性骨軟骨炎(OCD)は必ず存在すると言う症状はありません。
症状の進行の具合(病期)により様々な症状が生じます。
1.初期の症状
軟骨部分が剥がれたりしておらず比較的安定しているため
運動時や運動後の痛みや違和感が主となります。
2.進行期
進行していくと運動時痛が増悪したり、軟骨が痛むため炎症が生じ膝関節に水が溜まったりします。
軟骨部分が剥がれて不安定になると引っかかり感やロッキングと言う膝の曲げ伸ばしが急にできなくなる
ような症状が生じます。
2.離断性骨軟骨炎の分類
1.レントゲン(単純X線)
離断性骨軟骨炎を疑う時、まずレントゲンを撮ることが多いです。
レントゲンを撮る目的としては
・他の疾患の除外
・骨端線の評価
のために行われます。
骨端線の評価は今後の治療方針に影響してくるので確認する必要があります。
欧米では、Berndt and Hardy分類(距骨骨軟骨損傷でよく用いられる分類)がよく用いられていますが、
日本ではBruckl分類を用いる場合が多いです。
- Stage1→黎明期(れいめいき:症状の始まりの時):レントゲンでは判別できずMRIやCTで判別可能
- Stage2→透亮期(周囲に比べて黒く写る所見が見られる):レントゲンで透亮像が確認できる
- Stage3→分離期:母床との境界線の骨硬化が生じる
- Stage4→遊離期:母床から分離が見られる
- Stage5→遊離体形成期:遊離体の形成
病態的にも
初期に骨壊死(骨が痛む)→骨同士がぶつかり骨硬化(骨が硬くなる)→軟骨部分が剥がれる(Stage5)
と言う流れになります。
2.CT
CTでは3次元的に痛めている部分を把握することができ、遊離体の検出にも有用です。
3.MRI
単純X線で分からなかった部分を確認できます。
MRIでは骨軟骨片分離部に関節液が流人しているかどうかを見ることで
病変部の不安定性の程度を把握することができます
また痛めている部分のより詳細な情報もMRIでは確認することができます。
MRIでの評価が診断や評価には最も有用とされています!
MRI分類で有名なのはNelson分類でこの分類は手術方法の選択のためにも使われます!

3.見分けないといけない重要なポイント
OCD鑑別で注意しないといけないポイントは
正常の骨化核の不整像(Femoral condyle irregularit)です!!
Femoral condyle irreg-ularityとは小児期から成長期にみられ
単純X線像で大腿骨顆部の不整像が確認できます。
これをOCDの透亮像と見間違うことがあります!
Femoral condyle irregularitは成長の過程で見られる正常な過程で
軟骨下骨の不整像は成長とともに自然に消えていきます。
正常な過程のため病気ではありません!!
OCDと見間違いやすいですが鑑別ポイントとしては
・両側性
・OCDの好発年齢より若い(6~8歳)
の点に注意してみて行くことが重要とされています。
4.まとめ
今回は離断性骨軟骨炎の症状、診断基準についてご紹介しました。
診断に関しては、ドクターの仕事なので私たち理学療法士も専門ではありませんが
MRIやレントゲン画像を確認しドクターと治療方針を決めていく中でこのような知識を共有しています。
そして患者さんの症状と照らし合わせより良い治療戦略を立てています。
なぜ手術なのか?手術せずに大丈夫なのか??などの疑問は
今回の解説内容の情報で判断していきます。
次回は治療の進め方について解説したいと思います!
ではまた次回!!
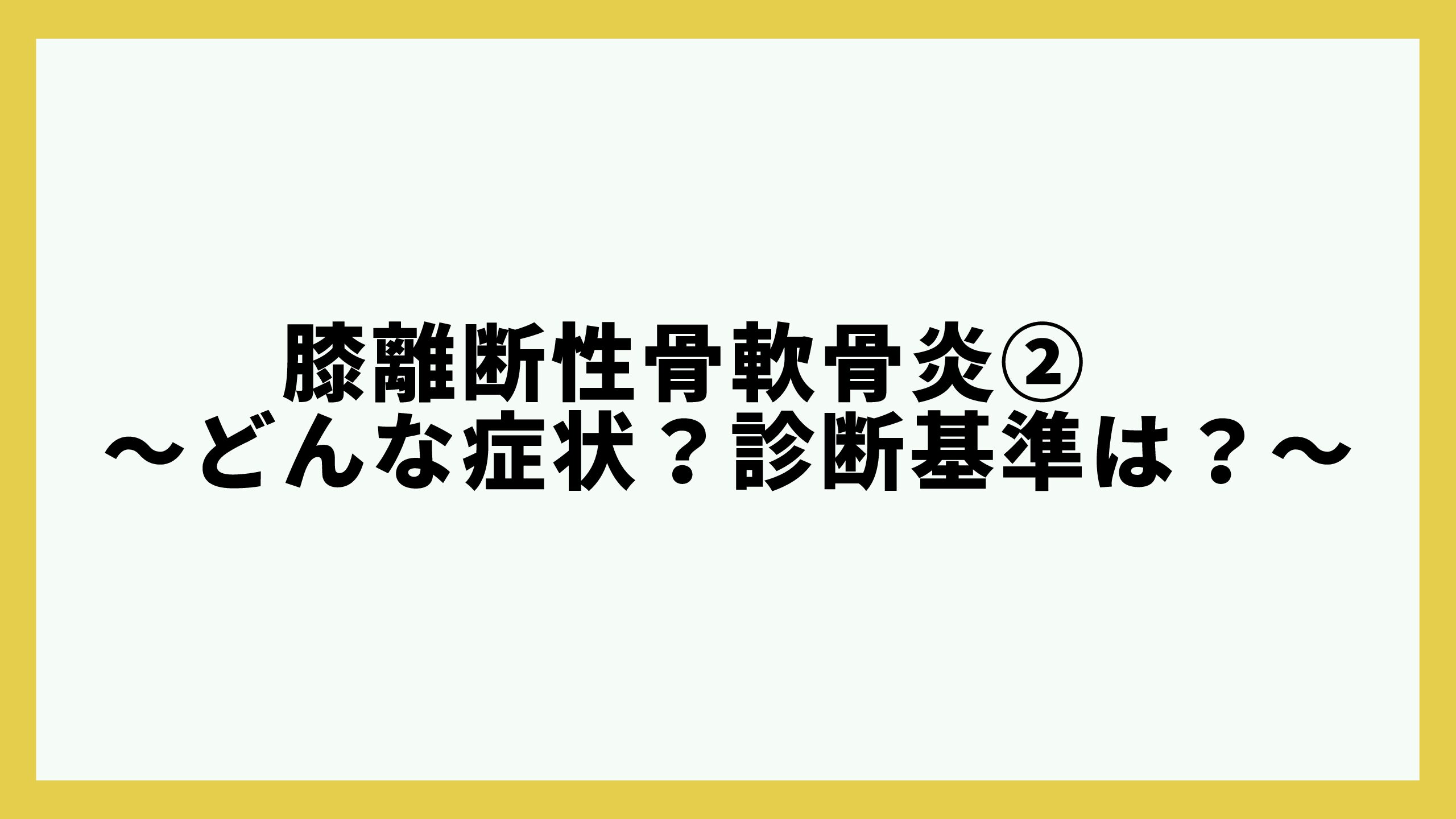
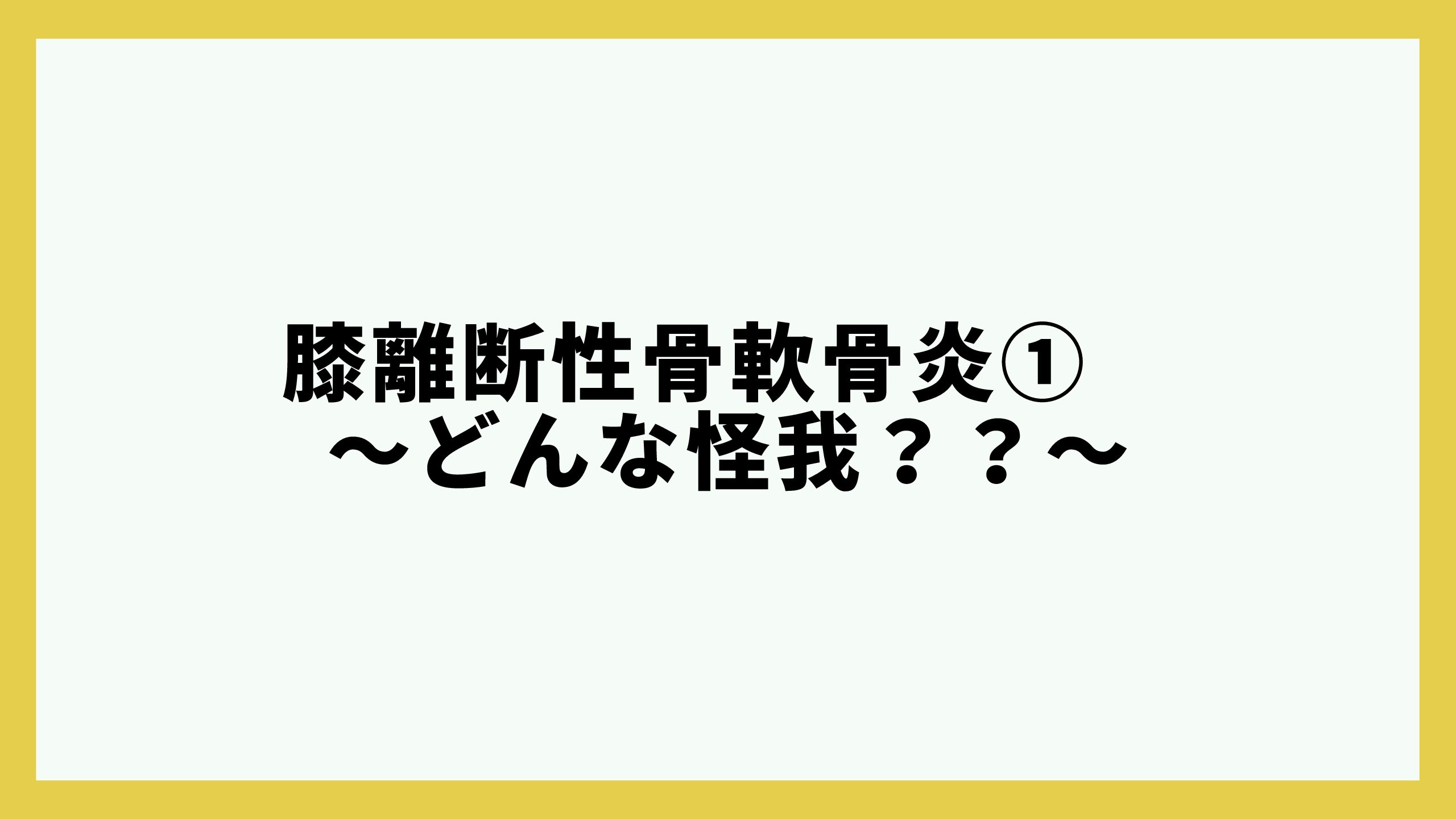
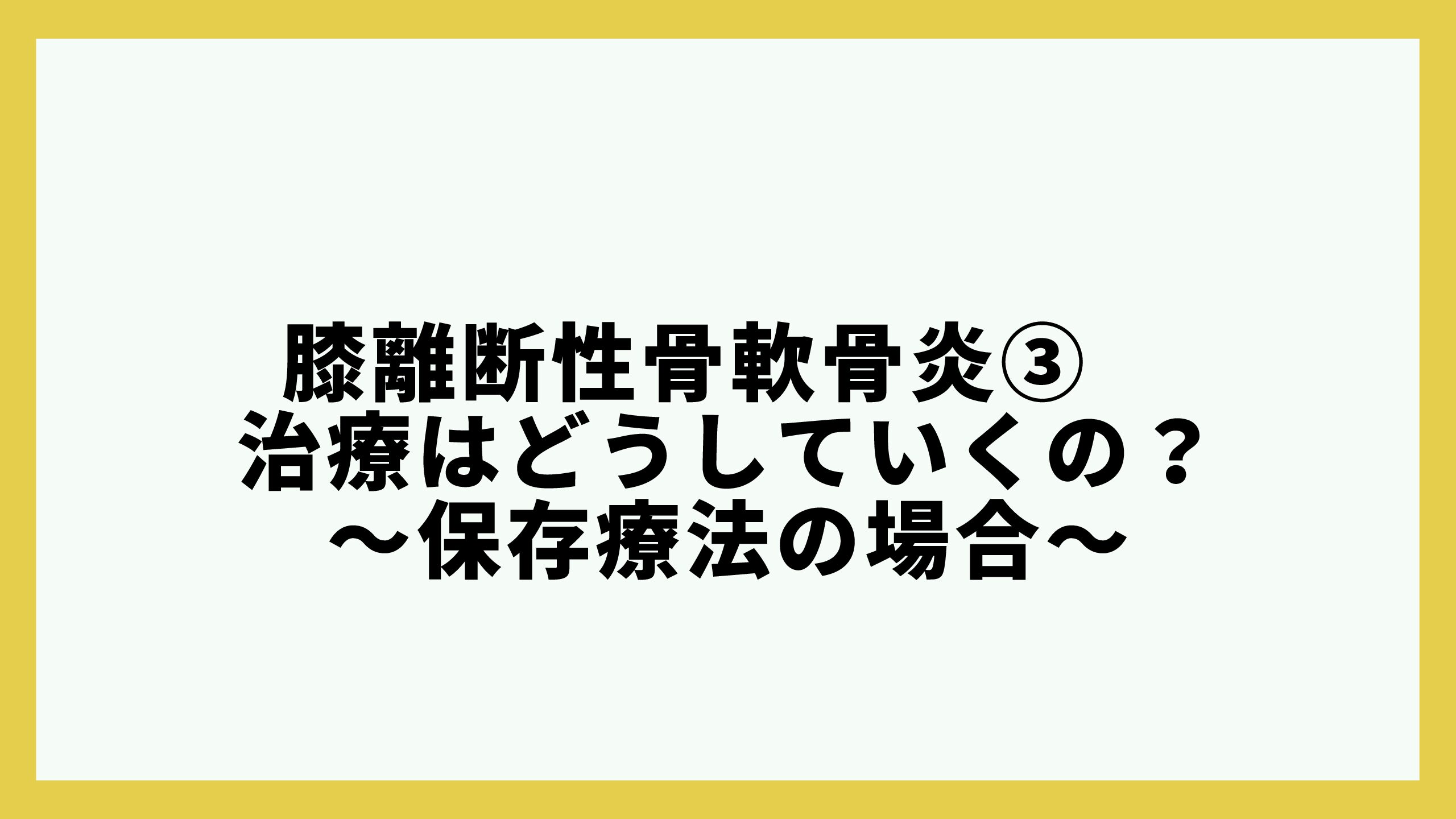
コメント